建物に関する登記
- 建物表題登記
建物を新築した場合や未登記のままになっている建物について建物登記簿謄本の表題部を作成する業務です。
- 建物滅失登記
建物を取り壊した(解体した)場合に必要な登記です。登記申請することによりその建物登記簿謄本が閉鎖されることになります。
- 建物合併登記
2つ以上の建物を1つの建物とする登記です。物理的に1つの建物とする(この場合は建物合体登記になります)のではなく、1つの建物登記簿謄本に複数の建物を纏めようという登記です。
例を挙げると、倉庫や車庫を自宅に付属する建物として1つの建物とする場合があげられます。こちらの登記はどんな建物同士でも可能な訳ではありませんので、詳しくはお問い合わせください。
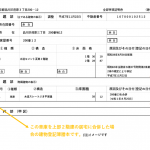
- 建物分割登記
上記の建物合併登記をした複数の建物を、今度は別々の建物とする登記になります。想定されるケースは、複数の建物を1つの建物としている場合に、そのうち1つの建物だけを売却する場合などが考えられます。複数の建物を全て同じ人に売却する場合などには必要ありません。
- 建物合体登記
建物合併登記とは変わって、物理的に複数の建物を1つの建物とする登記です。複数の建物の間を増築するなどして1つの建物とした場合に必要になります。
- 各種変更登記
建物登記簿謄本の表題部と言われている建物の場所や大きさ、構造などが変更された場合にその変更を建物登記簿謄本に反映させる登記です。
土地に関する登記
- 土地確定測量
土地を確定するための測量業務です。土地を売却する場合や、土地分筆登記をする場合に必要になります。
基本的には公共基準点を利用して測量をします。

- 土地現況測量
土地確定測量とは違い、その土地だけに着目し現況の測量をおこないます。そのため登記をするための測量図として使用することはできませんが、まず現地の状況を知り、建築計画を立てるような場合には有効な作業です。
- 土地分筆登記
1つの土地を複数の土地に分ける場合にする登記です。
- 土地合筆登記
土地分筆登記の反対で、複数の土地を1つにするための登記です。この登記は、複数の土地の上に1つの建物を建築する場合などに行われることがあります。
どのような土地同士でも合筆できるわけではありませんので、詳しくはお問い合わせください。
- 土地地目変更
土地登記簿謄本には、“地目”と呼ばれる欄があります。土地の利用状況を表す項目で、宅地や畑など23種類の中から判断します。利用状況が変わった場合には変更する義務があります。
- 土地滅失登記
土地がなくなった場合に必要になります。なくなる・・・?と思われるかもしれませんが、がけ崩れや海などへの水没によってなくなることがあります。
.png)